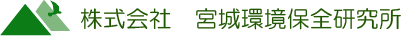日本全国の日当たりの良い山野に生えるオミナエシ科の多年草。かつては八幡町郊外の国見峠付近にもたくさん自生していたが、宅地開発や乱掘によりほとんど姿を消し、代わりに畑や家庭庭園での栽培ものが目立つようになった。野生のものが減少しているので、宮城県版レッドリストでは準絶滅危惧に指定されている。
オミナエシ(Patrinia scabiosaefolia)は漢字で女郎花と書く。その名は万葉集の用語「乎美奈幣之(おみなへし)」からきたもので、語源を推察するに、若い女性を意味する「をみな」に因んだものであることはおおよそ見当はつくが、「へし」はなにを意味するかはっきりしない。「へし」は「なるべし」の略で、清楚な花の姿を表わすという説もあるが、どうもこじつけのような気がしてならない。「をみなへし」はその後転訛して植物分類上の正式和名オミナエシになり、また俳句ではオミナメシで詠まれることが多く、※謡曲[女郎花]もオミナメシである。

オミナエシの根茎は太く、がっしりしていて移植に強い。背丈は1mほどの高さで、茎は細く弱々しく見えるが、かなり強靭で少々の暴風では倒伏しない。葉は対生につき、葉身は羽状に分かれ、裂片は狭く先端はとがる。初秋、茎の上部で分枝し、黄色い小粒の花を散房状にまるで傘を広げたように咲かせる。その開花の様子を紫式部は「花の色は蒸せる栗の如し」と表現したので栗花の異名がある。また、この花の咲く時期に合わせて盆花と呼ぶ地方もある。
オミナエシは秋の七種(ななくさ)の一つに数えられる。その七種類の草花を指定したのは山上憶良で、万葉集には次の歌が載る。
この2首は対句になっていて、七夕の宴席で憶良が即興的に披露したといわれる。秋の野に咲く美しい花を指折り数えてみれば、ハギ、ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウの7種であるがその意味である。万葉集には、この他オミナエシを題材とした歌が14首も収められている。秋の野につつましくも健気に咲くオミナエシは大和民族に大分人気があったようで、万葉集以降も古今集や枕草子、源氏物語などに度々登場する。
俳句では女郎花が初秋の季語であるが、前述のように「おみなめし」として作句する場合が多い。江戸期以降、著名な俳人の句が多い。
これらの句は、オミナエシの形態や生育環境を主体に詠まれているが、優しい容姿に似合わず、厳しい自然と対峙している様子も伺い知ることができる。なお、芭蕉の句の露けしとは、湿っぽいとか涙っぽいという意味の古語である。
同じオミナエシ科にオトコエシという草本がある。全体的にオミナエシに似るが、背丈はやや高めで茎も太く毛が密生し、花弁の色は白い。漢字では男郎花が当てられていて、オミナエシと同じような場所に自生する。
第1句の作者星野立子は高浜虚子の次女である。