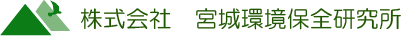中国から伝来した二十四節気によると、9月8日から22日までが白露(はくろ)。この時期の日中の気温は依然として高温であるが、夜間は長くなり、冷え込みも強まってくる。こうなると大気中に含まれる水蒸気の凝結は活発になり、これが翌朝の若葉に宿る露になるわけである。
新古今・秋上に所収の朝露の歌。かつて仙台市の東部に広がっていた宮城野原を歌枕にしている。
ちょうど白露の頃、大崎八幡宮の境内のあちこちに、赤い花を枝一杯に咲かせる低木が見られる。近寄ると、一種独特の臭気が漂い、クサギであることが分かる。また、咲いているのは花には違いないが、花弁の落ちた萼(がく)の部分で、これが赤い花のように見えるのである。庭木のように見えるこのクサギ、実は植栽したものではなく、近くの雑木林から野鳥が持ち込んだ種子によって繁殖した野生種である。日当たりの良い場所を好むようで、林縁部に多く見られる。
クサギの葉を手で揉み、匂いをかぐと強い匂いがする。もちろん、これが名前の語源でもある。この匂いは、葉や若枝に生える腺毛から発するもので、萌えたばかりの若い葉を茹でると、この悪臭はすっかり消え、山菜として食べている地方もある。いずれにしても、以前に紹介したヘクソカズラ(ヤイトバナ)と同様、人に嫌われる気の毒な名前の持ち主である。
クサギ(Clenodendron trichotomum)は、日本全国の低山帯に自生するクマツヅラ科の落葉低木。高さは通常2~3m、しかし肥沃な場所では直径20cm、高さ6mに達するものもある。学名を直訳すると「三つ又に分かれた運命の木」となるが、何を意味しているのか皆目検討がつかない。因みに、命名者は、235年前の安永年間に来日したスエーデンの植物学者ツンベルグである。
クサギは中国大陸にも分布していて、漢名は海州常山。実はこの名の由来もはっきりしていない。わが国でも中国の漢字に倣い、意味不明のまま昔から常山木の名を当てている。
クサギの樹皮は灰色で円い皮目が目立つ。小枝はやや太く、若い枝には軟毛が生える。葉は対生につき、どういうわけか相対する葉柄の長さは不同である。葉身は三角状心形でやや大型、強い臭気がある。8月、枝先に多数の集散花序を出し、芳香のある白い花を咲かせる。花弁の下方は細長い花筒となり、先端は5つに裂けて平開し、断片の間から4本の雄しべと1本の雌しべを突き出す。花冠が散った後も星型の萼は残り、その中央部にエンドウ豆ぐらいの果実を抱いて雪の降る頃まで宿存する。この萼は、次第に赤味を増して真紅に染まり、果実も美しい青紫色の球果に成熟し、そのコントラストは美事である。
「天災は忘れた頃にやってくる」とは、物理学者寺田寅彦博士の言葉。それにしても今年の3.11大震災は大き過ぎる天災であった。
寺田博士は、専門の物理学以外でも文筆家として知られ、多くの随筆集を残しておられる。30歳の頃に発表した「花物語」は、9種類の植物の話をまとめた随筆集であるが、その中に「常山(じょうざん)の木」を取り上げている。博士が昆虫採取に夢中になっていた小学生の頃の話で、当時住んでいた高知の城山のお堀ばたに一本の木があり、その幹にすがっている大きなカブトムシを捕らえた。得意になって家へ帰る途中、母親に連れられた小さな男の子が、いかにもそのカブトムシを欲しそうにしているので、気前良く呉れてやってしまい、後で後悔をしたというのがそのあらすじ。
この常山の木は、桃色の花を一杯に咲かせる木と書いてあるのでクサギであることは間違えない。それにしても大人でも知る人の少ないクサギの古名を小学生の頃、知っていたとは大変な驚きである。
歳時記では、常山木(くさぎ)の花が初秋、常山木の実が晩秋の季語。しかし、近年は、難解な常山木は嫌われ、臭木またはくさぎとして使われる傾向にある。
クサギの白い花弁には甘い芳香があり、いろいろな昆虫も集まる。
花期は8月から11月までと長いが、盛りは9月。白い花弁が落ちた後も赤い星形の萼が晩秋まで宿存するので、花期が長いように見えるのである。次の2句も、おそらくその萼を花に見立てて詠んだものと思われる。
真紅の萼に抱かれて熟す青紫色の果実もまた美しい。昔から、これを「常山木の実」と呼んで草木染に用いた。早稲のわらを灰汁にし、その中に実を入れて煮つめ、その汁を用いて浅黄色を出したといわれる。