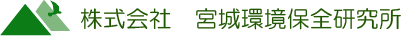一口にハギといってもその仲間はひじょうに多く、県内にはヤマハギ、ツクシハギ、キハギ、マルバハギ、イヌハギなど10種を超える野生種が分布する。これらのうち、私達が普通にハギと呼んで詩歌の題材とし、仲秋の名月に供えるのはヤマハギ(Lespedeza bicolor)とツクシハギ(L.homoloba)である。日本全土の山野に分布するマメ科の落葉低木で、八幡町界隈でも郊外に出れば、道ばた、荒れ地、林縁などいたるところに自生している。極めて丈夫な植物で、山火事の被災地や崖崩れの跡地などには、まっ先に侵入してくるパイオニア種である。
両種とも草丈は2m内外、多数の枝を分かち、葉は互生して3枚の小葉をつけ、小葉は楕円形で先端は丸い。花は枝先の葉腋から総状に出て、紅紫色の蝶形花をつける。ヤマハギとツクシハギの形態は良く似ていて識別はなかなか難しいが、小葉に厚みがあって花の色がやや淡色に見える方がツクシハギである。
万葉歌人山上憶良は、秋の野に咲く美しい花の代表7種を選んで紹介している。
これがいわゆる秋の七草で、憶良はその筆頭にハギの花を挙げている。この歌は五七七、五七七の旋頭歌の形式をとっていて、最後の句の朝顔の花はキキョウの花とされている。
万葉集は草木虫魚の世界といわれるように、いろいろな動植物が登場する。そうしたなかでハギを詠んだ歌が圧倒的に多く、141首を数える。身近な山野に咲くハギの花は、控えめではあるが気品があり、万葉人の嗜好に良く合っていたのであろう。

万葉時代、ハギは芽子という用字で使われていた。これは生え芽のことで、古い株から芽を出す様子に由来するといわれている。ハギを草冠(くさかんむり)に秋と書くようになるのは平安時代に入ってからで、秋を代表する草ということから作られた国字である。
俳句でハギといえば「一家に遊女も寝たり萩の月」の句がすぐに思い浮かぶ。松尾芭蕉が奥の細道を紀行中、北陸の親不知の近くの宿で西行伝説を聞いて作ったとされている。芭蕉に限らず当時有名な俳人たちは好んで旅に出ている。当然旅先では秋の野に咲くハギとの出会いも多かったと思われる。その人たちは次のような名句を残している。
ハギといえば古来、宮城野の萩が名高い。源氏物語の桐壷には
の歌がある。宮城野は、仙台市の若林区あたりから国府多賀城付近に広がる原野といわれ、昔から歌枕として使われてきた。その宮城野の小萩が宮城県の県花ミヤギノハギとする説もあるが、残念ながらそうであるとする根拠は見つかっていない。家庭庭園や公園に植栽されているミヤギノハギは、北陸地方に自然分布するケハギから作出された園芸種とする説が現在では有力となっている。宮城野の萩もヤマハギかツクシハギと考えて良いと思っている。