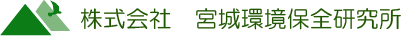長く続いていた梅雨は、ようやくあがり、いよいよ本格的な夏の到来である。7月27日から立秋前日の8月6日までは、24節気の一つ大暑となる。
ちょうどこの時期、郊外の雑木林の中に入ると、木肌がサルスベリに似て枝先に白い総状花をつけた低木に出合う。これがリョウブという木で、県内の里山ではサルナメシと呼んでいる。
リョウブは日本全国の低山帯に自生するリョウブ科の落葉低木。尾根筋など乾燥した瘠せ地に多く生え、ヤマツツジやナツハゼなどと群落を作る。土地条件の悪い場所に生えるため、成長はきわめて遅く、老木になっても樹高はせいぜい5m止まりに終わる。樹皮は茶褐色、表皮は薄く剥がれてまだら模様を描く。この滑らかな木肌に特徴があり、皮付きのまま床柱に利用され、また、この木で焼いた炭は良質で茶人に好まれる。
リョウブの枝は輪状に出て樹型は箒形になる。葉は枝の先に束生し、葉身は長卵状菱形で大きく、縁に鋭い鋸歯がある。花の咲く時期は盛夏、総状に花序を延ばし、小さな5花弁の微香のある白色花をたくさんつける。花の少ない猛暑のさ中に咲くので、近年は庭園木や公園樹に利用される。
リョウブは漢字で令法と書く。中国にこの木は分布しないので日本で作られた国字である。また昔は、ハタツモリと呼ばれていて、平安・室町期を通じ、この古名を題材とした和歌がたくさん詠まれている。
これは平安時代の歌集新撰六帖(1244年成)に載る恋歌である。ハタツモリが現在の和名リョウブに変わるのは、元禄時代の頃らしい。大和本草(貝原益軒著:1708年)などの文献に「救荒本草にして和名リョウブ、古名ハタツモリといへり」と出ている。
ところで判じものでもあるような令法やはたつもりの名前の出所は、元をただせばこの木の葉が重要な救荒食物であったことに由来する。話は少し長くなるが、昔の農民達は春になると近くの山に入り、リョウブの若葉を摘む慣わしがあった。その様子を詠んだ歌が前述の新撰六帖にも載っている。
収穫した若葉を釜で茹でて天日で乾燥させ、これを俵に詰めて天井などに保管して置き、救荒食糧として備えていたのである。ちなみに調理の仕方は、乾燥した葉を米と一緒に炊き、いわゆる令法(りょうぶ)飯(めし)にしたり、穀物の粉と混ぜて団子を作るなどして食べていたようである。
このように令法の葉は、古代から大切な救荒資源であったため、律令国家であった平安時代の中頃、農民に対し所有する畑の面積を基準に一定量のリョウブの植栽と葉の採取を命ずる官令が公布されている。実は、この官令つまり令法がそのままこの木の名前になり、また、畑の面積に応じ割り当て量を見積もるという官令の主旨を要約して、はたつもりの名になったものである。
リョウブの植栽は、凶作の年に備えるため江戸時代に入ってからも続けられており、米澤藩や肥後藩ではこれを盛んに奨励したという記録がある。
俳句では、「令法摘む」や「令法飯」が仲春の季題となっている。だが、いろりろな句集を紐解いても、これを季語とする作例は少なく、僅かに次の一句しか見つからなかった。
令法飯のレシピについては既に紹介しているが、その味は蕨(わらび)に似ているといわれるので、満更不味いものでないらしい。
リョウブを詠む句が上の一句だけでは少々寂しいので、今回もわが社の俳人達に吟行を願い、ひねり出していただいたのが次の句である。ただし、「令法の花」を盛夏の季題と勝手に設定してのことである。
第一・第二句はいろいろな欠点はあろうが、真夏の雑木林に咲くリョウブを実感で捉えた素直な句であり、また第三句は風通しの良い尾根筋のリョウブの木の下で下草刈り用の大鎌を研いでいる姿が目に浮かび、炎天下で働く保育作業の辛さが伝わってくる。