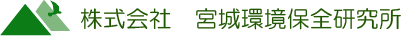夏が猛暑であればその冬は厳しい寒さになるといわれている。この冬もまさにそのとおりに推移し、寒い日が長く続いてきた。しかし、2月に入る頃から日脚は伸び、木の芽は脹らみを増し、4日には立春を迎えた。この頃から暦の上では、春になるので、春立つともいう。
万葉集巻10の冒頭を飾る「春の雑歌(ぞうか)」の中の1首で、作者は柿本人麻呂。蛇足ながらこの春の雑歌には、当時(680年代)、既にスギの植林が行われてきたことを示す次の歌も収められている。
今月の季題としたロウバイは中国の長江下流域の原産で、江戸時代の初期、朝鮮半島を経由してわが国に渡来した。花の乏しい真冬に咲くので庭木として珍重され、日本のほか、温帯地域の欧米諸国でも栽培されている。
ロウバイは、漢名の?梅をそのまま音読みしたもので、これが正式の和名となった。名前の由来は?細工の梅の花に見立てたものとも、臘月(陰暦の12月)に梅に似た花を咲かせるからともいわれる。因みに、英名は花の甘い香りに注目してウインタースイート(winter sweet)である。 ロウバイは、原産地の中国でも北宋時代から庭園に植えられていたようで、蘇東坂など多くの詩人によって詠まれており、次の黄庭堅の詩の一節はよく知られる。
金梅はロウバイのことである。
ロウバイ(Chimonanthus praecox)は、高さ4mほどになる落葉低木。名前にウメの字が入るが、ウメの仲間(バラ科)ではなく、モクレン科に近縁のロウバイ科の植物である。属名は、ギリシャ語で冬の花、種小名は早咲きを意味し、花の咲く時期を表わしている。
樹形は株立ち状になり、さかんに分枝する。樹皮には小さな楕円状の皮目がつく。葉は対生、葉身はやや大型の楕円形で先が尖り、全円で表面は著しくざらつく。表面の葉脈は凹み、裏面に突出する。

花期は1~2月、葉の出る前、長く伸びる小枝に径2cmほどの甘い香りの花を横向きにつける。花被片は透きとおり?細工のようで艶がある。多数ある花被片のうち外側のものは淡黄色で長いが、内側のものは、黒紫色で短い。雄しべは5,6本、雌しべは多数で、壷状に凹んだ花托の中にある。花後、花托は生長して4cmほどの褐色のミノムシに似る偽果となり、その内部に飴色をした大豆ほどの種子が10個ほど入る。乾燥した偽果を揺らすとカラカラと音がする。 ちょうど大寒の日、読売新聞のコラムに、ロウバイの花が咲き始めたという記事とともに、次の句が紹介されていた。
厳寒のさ中、立春を待ちかねたようにあわてふためいて咲くロウバイに狼狽を掛けた句で、川柳のようでもあるが、作るに難しく、聞いて納得するうまい句だとすっかり感心してしまった。 一年で最も冷え込みの厳しい頃に咲くロウバイは、冬枯れの庭を飾る数少ない花木である。臘梅が、この時期の季語になっていて、明治期以降、多くの句が作られている。
ロウバイの花は、前年枝の葉腋に1個づつ横向きに咲かせ、琥珀のような色艶がある。株全体をイルミネーションのように彩る様子は壮観である。第3句の淡海は琵琶湖沿岸をあらわし滋賀県のことである。
ロウバイの花には上品な香りがある。晴れた日には、ことのほかよく薫る。両句とも、路地に咲くロウバイの近くを通った時のものと思われ、第2句の作者は現在、朝日俳壇で選者をつとめておられる。
低木ではあるが、ロウバイは盛んに分枝し、枝は勢いよく四方に開出する。その様子を「雪うち透かす」や「枝さしかわし」と格調高く表現している。東京の田端に住んでいた芥川龍之介の家の裏庭には、一株のロウバイの木があったと本人が記述している。
ロウバイは、社寺の境内でもよく見かける。第2句斎庭は祭りの庭で斎場のこと。
花が終わった後の薄みどりの葉のひろがり行く様子を詠んだ歌で、ここだくはこれほど多くのという意である。ロウバイの葉は大きくなるとざらつき、紙やすりの代用になる。