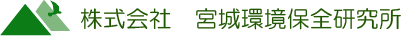ロンドンオリンピックが閉幕して数日後、朝日新聞のコラムに、「植物図鑑を書き換えたい。ナデシコはもう花の名前を超えている。女子サッカーの悲願がロンドンオリンピックで咲いた」と載っていた。
思えば未曾有といわれた3・11大震災以降、夢も希望も失いかけていた被災地の人たちに大きな元気を与えてくれたのが、ナデシコジャパンのW杯優勝であった。外国勢はフロックと思っていたようだが、それがどうしてロンドン五輪でも強敵を次々になぎ倒し、決勝では3連覇を目指す米国に敗れはしたものの、その健闘は見事なものであった。冒頭のコラムは強靭な精神力で銀メダルに輝いた女子選手たちに、たおやかな意味を持つナデシコの名は不似合いだというのである。

ナデシコは、いかにも撫でてやりたいような可憐な草花である。平安時代の古書に「鐘愛衆草に抽(ぬ)きんず。故に撫子という」と出ている。そのナデシコがはじめて現れるのは万葉集。撫子、瞿麦、奈泥之故などの用字で26首も詠まれている。そのなかでも、作者は不明であるが、次の歌は佳作としてよく知られる。
野原に出てみればナデシコの花が一面咲きほこっている。待ちわびていた秋がようやく近づいてきたらしいと素直な調べでうたっている。
同じ万葉集に、自然歌人山上憶良の秋の七草の歌がある。
憶良はナデシコを、秋を代表する草花の一つに取り上げている。
ナデシコは万葉期以降も勅撰歌集などに数多く詠まれている。
そのなかでも、特に有名なのが次の歌。
実にわかり易い歌で、作者は平安時代に36歌仙の一人といわれた素性法師。昔、中学で教わった「見わたせば柳桜をこきまぜてみやこぞ春の錦なりけり」もこの人の作。
ナデシコはナデシコ科ナデシコ属(Dianthus)の多年草。正式な和名をカワラナデシコという。和名の形容句カワラは生育環境を示し、日当たりの良い河原の石礫地に好んで生える。別名のヤマトナデシコは淑やかな日本女性の美称にたとえたもの。本州、四国、九州の低山帯に分布し、北海道には自生しない。漢字で瞿麦と書き、万葉時代からこの字が使われている。なお、撫子は慣用的に使われている当て字である。
ナデシコと同属で中国原産のカラナデシコの漢名は石竹(せきちく)。清少納言の随筆「枕草子」に「草の花はなでしこ。唐はさらなり。大和のもめでたし」とあるので、石竹は古くからわが国に渡来していたことがわかる。因に、オランダ石竹はカーネーションのこと。
ナデシコは全草粉白色を帯び数本の茎が叢生して高さは30~80cm。膨らむ節があり、ここから細長い葉身を対生に伸ばす。8月から10月にかけて茎の上方に側枝を出し、先端に直径5㎝ほどの淡紅色の花を咲かせる。花弁は5枚、平開して縁は糸状に裂ける。果実は蒴果で先端は4裂し、黒色の小さな種子を散らす。この種子を漢方で瞿麦子(くばくし)と称し消炎、利尿の治療に用いる。

山上憶良はナデシコを秋の七草としてうたうが、同じ万葉集でも夏の花として詠むものもあり、季節の分類ははっきりしていない。この傾向が平安期以降の和歌集にもみられるのは、ナデシコの花期が夏から晩秋まで長く咲き続けることに原因があると思っている。
これに対し、俳句歳時記では、江戸初期以降、伝統的にナデシコを夏の植物として扱っている。これは元禄時代の「季寄せ集」を根拠としており、この資料では撫子をはじめ川原撫子、大和撫子、唐撫子、藤撫子、常夏、石竹などの異名も夏の季語としている。
以下、ナデシコを題材とした著名な作家の句をいくつか紹介する。
これらは元禄時代に活躍した芭蕉一門の句。総帥芭蕉の句は酒に酔い、ナデシコの花が咲く川原の石の上に寝そべってみたいとする願望を詠じており、また、第2句はナデシコの華麗なあで姿をうたったもの。なお、第3句は、八重咲きとあるので、当時オランダから渡来したばかりの紅夷石竹(カーネーション)のことである。
芭蕉没後、120年ほど経過した江戸中期の句。上記二人の作者には親交があったようで、一茶が江戸に出てきたときには、必ず成美の家に寄宿したといわれる。第1句は優美に咲いたナデシコであっても節々は逞しいことを強調しており、第2句は一茶らしい軽妙洒脱な句である。
これらは明治期以降の近代句。第1及び第2句の石竹は、中国原産のカラナデシコのことで、背丈は30㎝内外、花は高盆型で初夏に咲く。第3句はナデシコの自生する自然環境を巧みに捉えており、第4句は秋の句とするのが妥当と思われる。