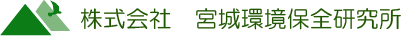一休和尚の戯歌として伝わる。若い頃はさほど気にかけてはいなかったが、馬齢を重ね老境に入ると、まさにその通りと感じるようになった。
門松といえば昨年の暮れ、地元紙の県内版に藩制期の仙台城に飾られた伝統門松の記事が載っていた。一般的な門松は、斜めに切った孟宗竹に松の枝を組み合わせて作るが、仙台藩では、高さ3mほどの栗の木を柱に笹と松を添えたものであった。この門松は、代々藩有林の管理にあたっていた根白石の山守の家で製作し、献上されていたとのこと。
この伝統門松に使った笹の種類は明らかではないが、材料はすべて地元産を用いたとされるので、おそらく付近に自生するヤダケかアズマネザサであったろうと推測している。
そこで今回は、瑞祥植物としても知られるヤダケを取り上げてみた。
竹や笹は、記紀万葉の時代から歌や物語に登場し、日本民族との付き合いは長い。しかし古今集に
の歌があるように、昔から竹を木の仲間に入れるべきか、草の仲間にすべきかで、人々を悩ませきた植物である。

だいぶ前の話で恐縮だが、私が県の林業関係の職場に在籍していた頃、学校緑化コンクールの審査で、近くの中山中学校にお邪魔したことがある。審査が終わったあと、環境緑化に熱心な校長先生から、校木を矢竹(ヤタケ)にしたいのだがという相談を受けた。新興団地に開校したばかりの中山中の校章は、協調や連帯を強める必要のあることから、毛利元就(もうりもとなり)の故事にならい三本の矢としている。ついては校木も校章ゆかりの矢竹にしたいのだが、竹が草であっては困るというものであった。
竹が木か草かについては現在でも意見が分かれる難しい問題である。私は校長先生の期待に迎合したわけではないが、林業関係者の多くは、建築資材や海産物の養殖資材に伐り出した竹の稈を竹材、筍を生産する竹薮を竹林と呼ぶように、竹を木材として認知していることや、ほとんどの植物図鑑は、竹を木の仲間として取り扱っていることなどを話したところ、私の説が採用されることになり、中山中学校の校木は、矢竹に決まったのである。蛇足ながら中山中学校は後日、宮城県学校緑化コンクールで最優秀賞の栄誉に輝いている。
イネ科の植物のうち、多年生で茎(稈)が木質化するものをタケ亜科に分類し、一般に木の仲間に入れている。タケ亜科は更に稈鞘(筍の皮)が茎から直ぐ剥がれ落ちるものをタケ類、そのまま茎に残るものササ類として分類する。ヤダケは名前に竹の字がつくが、稈鞘が長く宿存するのでササの仲間ということになる。
ヤダケ(pseudosasa japonica)は北海道を除く日本全域及び朝鮮半島南部に自生し、低山帯から沿海部にかけて分布する。稈高は2~5m、径は5~15mmで節は低く、節間が長いので古くから矢柄に利用され、また神事、日用品、釣竿などにも広く用いられてきた。なお花序は側枝に頂生して5~10花をつけるも、滅多に開花はしない。
ヤダケが離島に多く分布するのは全国的な傾向で、しかも各地に似たような伝説が残る。それは、某かという弓の名手がいて、本土から離島に向けて矢を放ったところ、狙い通り地面に突き刺さり、それが根を出し繁茂したというもの。本県でも網地島、田代島、福浦島にはヤダケの大群落が見られる。

万葉集では、ササをささ(小竹)あるいはしの(細竹)と詠み、タケとは区別している。小竹または細竹とある歌は17首を数え、なかでも次の歌はよく知られる。
歌聖柿本人麿が任地の石見国で娶った現地妻、依羅娘子(よさみのおとめ)と別れ、大和の都へ帰る途上の山中で詠んだ歌。ささの葉の音がさやさやと全山になびいているが、私は今、別れてきたばかりの妻のことを思うと悲しみでいっぱいであるという意。風がささの葉にあたる音をさやさやと表現したのは、この歌がはじまりといわれる。
石見国に生えていたささの種類は不明であるが、次の歌は明らかにヤダケを詠んでいる。
難しい歌のようであるが題詞に譬喩(ひゆ)歌とあるので、細竹を恋しい人と読み替えれば、恋に悩む男の歌ということがわかる。つまり近江の八橋の細竹(ヤダケ)を矢に作らないで、(あの女を私の妻にしないで)ほんとうに私は堪えることができようか、こんなに恋しいものをということ。八橋は近江八景の一つ「矢橋」で、周辺にはヤダケが密生していたと伝わる。因みに、万葉集には竹を詠む歌は21首を数える。
一方俳句歳時記では、竹も笹も一括して竹として句が作られている。竹類は、他の植物と異なり、古い葉が落ちて新葉が出るのは夏から秋にかけてであり、この葉替わりの時期を「竹の春」と称し、これを季語としている。ただし、一斉に落葉するわけではないので、普段は気づかないことが多い。竹の句のうち、ヤダケを詠んだと思われるものを2、3紹介する。
ヤダケは真っ直ぐに伸びしかも容姿端麗なので大名竹とも呼ばれ、庭園、社寺、城跡などに植栽される。掲句は、垣根や目隠しに植えられたヤダケの葉替わりを詠んだ句である。