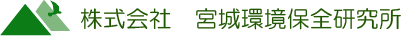今年のヤマユリの開花は見事なようで、地元紙は、仙台市野草園や大衡村昭和万葉の森のその様子を大きく報じている。八幡界隈の保存緑地にも、さながら「草深百合」のように、あちこちに白い大輪の花を覗かせている。今回の季題は盛夏に咲くヤマユリを取り上げてみた。
洋の東西を通じてユリの文化史は古代に遡る。アダムの妻イヴが禁断の実を食べてエデンの楽園を追われたとき、悔恨のあまりに流した涙がユリの花に変わったというのは旧約聖書の話。転じてわが国では、最古の書・古事記に「狭伊(さい)」の名で登場する。同書の中巻に、初代神武天皇が、大和の豪族・大物主神の娘・伊須気余理(いすけより)姫を皇后に娶る話が載る。それによると、姫は山百合が繁る狭伊川の辺りに住んでいて、その川の名が、当時の山百合であったという。古事記に詳しい作家の田辺聖子は、この物語の姫を「山百合姫」と呼び、分かり易く解説している。

飛鳥時代に入ると、狭伊の名は百合(ゆり)に変わる。百合は、その頃中国から伝わった漢名で、地下の球根が多数の鱗片の塊で出来ていることに由来する。同時代に編集された万葉集には「草深百合」や「さ百合」の名で10首詠まれており、次の歌は明らかにヤマユリを詠んだものである。
草むらの中に咲くヤマユリの花は、隠れていてもはっきりと目立つ。そのヤマユリのように、少しほほ笑みかけただけで、私を妻というべきでしょうか。そんなことはないでしょうにと、求婚を拒否している女性の歌。
防人に召され、故郷の常陸(ひたち)国を出立した男が、後に残した愛妻を思慕して作った歌。方言丸出しながら、切々とした心情が胸に迫るものがあり、しかも、「ゆる」のユと「ゆとこ」のユの同音を繰り返してリズムを整えるなど、技巧的にも優れた歌である。ところで、古典に詠まれる「さ百合」は一般的にササユリとするのが定説だが、このユリの分布域は西日本に限られ、筑波山には自生しない。従って、この防人が歌うさ百合は、ヤマユリとするのが妥当といえる。
平安・室町期の歌集にも百合の歌は多数入首するが、ほとんどが「さ百合」として歌われ、山百合が再び登場するのは近世のこと。
順に「柿園詠草」、「むらさき」、「恋ごろも」に所収。三句目のしろ百合を鉄砲百合とする説もあるが、歌の調子からすれば、ヤマユリの方が相応しい。
ヤマユリ(Lilium auratum)は、ユリ科ユリ属の多年草。近畿から東北地方の丘陵及び山地帯に分布し、草地や林縁、疎林地などの半日陰の地を好む。わが国の特産種であるが、華麗な花が好かれ、世界各地で栽培される。
地中に肉厚な鱗片葉の多数重なる球茎があり、その中心から一本の直立茎を伸ばす。高さは1~1.5m、葉は互生し、葉身は披針形で光沢がある。7~8月、茎の先に数~十数個の白色の花を横向きに咲かせる。花形は大きな漏斗状で花冠の直径は20~25㎝、強い芳香がある。花被片は6個、先端が細くなって反転し、中央に金色の条が入り、内面に赤い斑点が散らばる。雄しべは6本。先端につく花粉は紅褐色。蒴果は円柱形で内部に偏平の種子が多数入る。
ユリ属はすべて鱗茎植物で、わが国には12種あり、県内には、ヤマユリ、オニユリ、コオニユリ、スカシユリ、ヤマスカシユリ、クルマユリ、ヒメサユリの7種が自生する。

ヤマユリの花は、ユリ属の中でも最も美しく芳香もあるので、単に百合といえばヤマユリを指す。幕末の開国時に来日したイギリスの園芸家たちは、わが国のヤマユリの花の見事さに驚き、球根を持ち帰って育て、これを1862年に開催されたロンドンのフラワーショウに出品したところ、大変な好評を得て、賞牌も受けたといわれる。この時、ヤマユリの花をはじめて見たロンドン大学植物学教授のリンドリー博士は、ヤマユリの花被片の中央に入る金色の条に注目しLilium auratum(黄金の百合)の学名を与えた。以来、欧米では、ヤマユリをgolden lilyと呼び栽培が盛んになった。大正元年には、横浜の種苗会社一社で1500万個の球根を輸出したという記録がある。
俗言に「立てば芍薬、座れば牡丹、歩む姿は百合の花」がある。百合の花は容姿端麗なばかりでなく、清楚な趣きもあり、かっては、女子の名前に百合をつけることが多かった。さしずめ、吉永小百合や小池百合子などは、名前負けのしない上品な御方とお見受けする。
俳句歳時記では、百合(山百合)、さゆり(笹百合)、鬼百合、姫百合、鹿の子百合、鉄砲百合などが夏の季題にされ、そのうち百合を詠む句が最も多い。まずは江戸期の句から紹介する。
支考は蕉門の十哲のひとりで「ひだるさ」とは腹を減らして元気のない様子をいう。また、一茶の句は曇天の野に咲く山百合のことと思われる。以下は明治期以降の作。
山野に咲く山百合にいろいろな気象用語を組み合わせた句。
百合の花には強い芳香があり誰にも好まれる。まさに偽りのない香である。
向こう岸に咲く山百合をなん本か手折り、それを片手で捧げて川の淀みを泳いでくる子供の様子を詠んだ句。昔は、このような光景はよく見られていたもので、郷愁が感じられる。