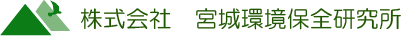厳しい寒さの中、山林の地表に青々と茂っているのがヤブコウジ(Ardisia japonica)である。里山のスギ林の林床に多く見られるが、海岸林の内部や奥山のブナ林の下にも生育し、分布域はかなり広い。大崎八幡宮境内の老杉が立ち並ぶ林床にもあちこちに群落を作っており、ちょうど今が赤い実の見頃となっていて、冬枯れの景色に明るい彩を添えている。
漢字では藪柑子と書く。コウジとは11代垂仁帝(すいにんてい)の御世、田道間守(たじまもり)が常世の国から探し求めてきたコウジミカンのことで、ヤブコウジの葉や実がこれと良く似ていることでついた名といわれる(※)。古くから盆栽や庭園にも植えられ、俳諧では冬の季語としている。
文献によると、ヤブコウジは江戸時代に園芸品として扱われ、特に盆栽が異常な人気を博し、高値で取引されていたようである。ところが不思議なことに、当時の句作例に盆栽はおろか自生に関するものまで全く見当たらない。ヤブコウジが冬の季語として登場するのは近世になってからで、上の句は、いずれも大正期以降の作である。赤い実の鮮やかさを歌った句として、「雪すこしとけて珊瑚かやぶこうじ」もある。

話は変わるが、マンリョウ、センリョウと大金の名のつく植物がある。両種とも正式の和名で、赤い果実が美しく庭園木や鉢植えにして鑑賞する。同じように赤く美しい実をつける植物を、昔の貨幣単位になぞらえて、カラタチバナを百両、ヤブコウジを十両、ツルアリドウシを一両と呼ぶ。いずれも実の大きさや美しさは大同小異であるから、この値ぶみは背丈の高さで決められたものらしい。因みに、センリョウはセンリョウ科、ツルアリドウシはアカネ科のもので、他はすべてヤブコウジ科の植物である。

十両の値がつくヤブコウジは草本と見紛うばかりに小さな常緑の木本である。茎は地面を這い、その先端は立ち上がるが高さはせいぜい30cm以下、枝先の上部2節ほどに楕円形の葉を数枚輪生する。盛夏の頃、その葉腋に白色の小さな花を数個下向きにつける。これが冬になると赤いつやつやした実に熟し、濃緑の葉とのコントラストが美しい。この緑葉紅実のヤブコウジは昔から瑞祥の縁起物として蓬莱台(ほうらいだい)の上などに飾られ、正月の祝儀に良く使われてきた。
和歌の世界では、俳諧と違って古くから歌の題材となっており、万葉集ではヤマタチバナとして詠まれている。大伴家持は師走に降る雪を見て、次の歌を作っている。
この雪が消えてしまわぬうちに、さあ早く山へ行こう。ヤブコウジの赤い実が雪の間から美しく照り輝いている姿を見るために、というのが歌意。わざわざ赤い実を見るために、寒い雪の中を歩いていこうとする健康的な歌である。当時の人々は、ひそやかに照り輝くヤブコウジの実に大変な魅力を感じていたようで、古今集に紀友則(きのとものり)は次の歌を残している。