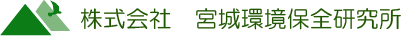北海道から沖縄に至る日本全土に分布するイネ科の多年草。陽あたりの良い草地や河原を好み、埋立地や海岸の砂地にも生える。とにかく丈夫な雑草で、里地や都市部の自然環境が牧草地から逃げ出したウシノケグサ、カモガヤ、シロツメクサなどの外来種に占有されつつあるなか、ひとり気を吐き居直っている在来種である。

チガヤ(Imperata cylindrica var. koenigii)は晩春、地下を横走する根茎から50cmほどの稈を伸ばして群生する。2~3枚の葉が根生し、細長い線形で先は尖る。稈の先端につく花穂の長さは15cm内外、それを構成する小花穂は互いに中軸に寄り沿うので、花序全体が円柱形になる。
若い時期の花穂が黄褐色に見えるのは、小花穂の葯の色で、後に成熟すると銀色に変わり、太陽に輝く様は美しい。
チガヤが強靭な雑草である由縁は、地下茎のたくましい生命力と、花穂につく旺盛な繁殖力による。硬い鱗片に包まれる地下茎は、少々固く堆積した荒地にも容易に入り込み、それが強力なネットワークを形成し、他の植物の侵入を阻止している。また種子には、銀色の長毛が密生しており、これが風を利して舞い上がり、遠隔の地にまで飛散して勢力圏を広げる。
チガヤの花穂は茅花(つばな)、その群落は浅茅原(あさぢはら)と呼ばれ、昔から身近で見られる自然の植物として知られていた。また、物語や詩歌にも数多く取り上げられてきた。わが国最古の歌集万葉集には、チガヤに関する歌が26首も収められている。その中にチガヤを題材としてやりとりされた面白い歌があるので紹介してみる。
紀女郎(きのいらつめ)が大伴家持に贈った相聞歌である。戯奴とは人を卑しめて呼ぶ言葉で、ここでは若造という意味で使っている。「お前さんのために、わざわざ春の野で摘んできたチガヤです。これを召し上がって太りなさい。」というのが大意。チガヤの花茎には甘味があり、今でも子供たちはこれを食べている。
これが郎女への返歌。「わが君様にこの若造は大分恋しているらしゅうございます。頂戴したチガヤを食べてもますます瘠せるばかりでございます。」と恋の苦しみを告白している。この二人が交わした歌は、春の相聞に入首しているので恋歌ともとれるが、当時郎女は、初老の域に達していたはずであり、若い家持が本気でこの歌を返したとは考えにくい。おそらく戯奴とか、わが君のようにお互いを誇張した表現で呼び合っていることからも、この歌は単なる歌遊びとしてみるのが妥当なのであろう。
チガヤを詠んだ歌として最も有名な万葉歌。作者の旅人は家持の父で、当時大宰府長官の職にあった。浅茅原(あさぢはら)のつばなを同音のつばら(委細)にかけ、それを導く序詞として使っている。「つくづく物思いをしていると、ふるさとの奈良の様子があれこれと心に浮かんでくる。」という意味である。
万葉集での茅花や浅茅原は、恋歌か印象的な叙景として読まれるが、源氏物語以降になると、その使い方に微妙な変化が認められる。例えば紫式部は、「かかるままに浅茅は庭の面も見えず」と記し、平家物語には、「旧き都にきてみれば浅茅が原とぞなりにけり」とあるように、チガヤの生える原は、もっぱら荒廃の象徴として描写されるようになる。これは文明が進むにつれて、自然に対する見方も変わってきたことを表わしている。
茅花を題材にした江戸期の俳句では次の句が知られる。
作者は天明期の俳人で、川中島の古戦場を懐古している句。千曲川の岸辺にたなびく銀色の穂が、秋の斜陽に輝いている風景をうたっている。
以上3句は、近世の句である。