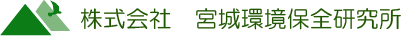草の仲間は、生活様式によって多年草と一年草に分けられる。多年草は、地上の茎や葉が枯れても地下の組織はそのまま残り、翌年再び芽を出して成長するものである。これに対し、一年草は種子から発芽・成長し、枯れるまでの期間が1年以内のものである。その大部分は春から秋までを生活期間とするが、なかには秋に発芽して冬を越し、翌年の夏までを生育期間とするものもある。こうした2年越しに生活するものを越年草と呼んでいる。

ナズナ(Capsella bursa-pastoris)はその越年草の代表である。仲秋を過ぎる頃に芽を出し、根生葉という切れ込みのある細長い葉をロゼット状に広げて冬を越す。翌春、根生葉から茎を伸ばし、その上部に白い4枚の花弁の小さな花を総状につける。花後の果実は平たく小さな三角形になるため、これを三味線のバチに見立ててペンペン草の異名がある。ナズナの名の由来には愛らしい菜という意味の撫菜(なでな)からきたとする説と、早春に咲いて夏には枯れるため、夏無き草の転訛とする説がある。

ナズナはダイコンやキャベツなどと同じアブラナ科の植物である。畑の内外、道ばた、空地や公園など至るところに生える雑草で、まさに「雑草のように強くたくましく」の表現が似合う強い生命力を持つ。
日本全土に分布するが、もともとは縄文時代にムギなどの畑作物と一緒にメソポタミヤから中国経由で伝来した史前帰化植物と考えられている。
芹(せり)・薺(なずな)・御行(ごぎょう)・はこべら・佛の座・菘(すずな)・すずしろ
これが御存じ春の七草である。これらのうち、「ごぎょう」はハハコグサ(キク科)、「はこべら」はハコベ(ナデシコ科)、「ほとけのざ」はコオニタビラコ(キク科)のことで、「すずな・すずしろ」はカブとダイコン(ともにアブラナ科)の美称である。この七草の葉を粥に入れ、正月7日に食べる風習は全国的に広まっている。これを七草粥といい、その起源は古く、延喜式や枕草子にも記述してあるので、平安時代の初期には行われていたようである。それ以降も、「正月に七草の羹(あつもの)を食すれば万病なし」ともてはやされ、寒中の健康食として現代まで伝わっているものと思われる。
七草粥に入れるナズナは、根生葉の部分を摘み取って利用する。このナズナを摘み取る風情を描写した句が多く作られている。
二句目の賎が子とは、貧しい家庭の子を指し、そのような子供達は摘み馴れているのでナズナを識別する眼を持っているということ。実際にナズナの葉の形には変異が多く、見分けるには大変な苦労をする。また3句目はまさにその通りで、ナズナは新しく掘り起こした軟らかい土の上に旺盛に繁茂する性質がある。
七草粥に入れる材料は、食べる前の晩に刻むのがしきたりである。爼の上に菜をのせ、その地方に伝わる※「七草囃子」を唱えながら、包丁でトン、トン、トンと刻む。この行事を薺打ちや宵薺と称するので、ナズナは七草の主役と考えてよい。
第1句は、はやし言葉を唱えながら勢い良く包丁を叩くので、薺の切れ端が四散する様子を歌ったもの。2句目の「くひな」は湿地に住む夏鳥のクイナ(水鶏)をかけ言葉にしていて、この鳥はキョッ、キョッ、キョッと声高に物を叩くように鳴くので、俳句では「くひなたたく」と表現されている。また第3句は、本来、前の晩に行うべき薺打ちをうっかり忘れてしまい、次の日にあたりをはばかるようにして俎板を叩いている若い主婦の句と思われる。