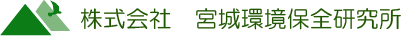4月5日から19日までが、二十四節気の一つ清明。清浄明潔の略とされ、万物すべて新鮮に感じる。仙台周辺で染井吉野が開花するのもこの季節。八幡町界隈に残る雑木林の林内には、早咲きのマンサクやキブシの後を追うように、クロモジが同じ黄色の花を綻ばせている。
冬木立ちの中に咲くクロモジの生態を一言でまとめた季節感あふれる歌である。
クロモジと聞けば、誰でも高級和菓子に添えられる皮付きの楊子を思い浮かべるであろう。クロモジの材には独特の芳香があり、材質緻密で削り易く、昔から爪楊子にされ、黒文字の別称で使われてきた。
クロモジの名の由来は、この木の枝に付着する※地衣類の描く黒い模様を文字に見立てたとするのが、通説である。だが、クロモジのモジは古くから使われている女房詞(ことば)からきているとする異論も有力だ。平安期以降、宮中などに仕える女房(女官)たちは、日常生活で使う言葉のうち、直接その名を口にするのがはばかられる場合、その用語の一部に「もじ」を加えて呼ぶ習わしがあり、それを女房詞と称していた。杓子をしゃもじ、髪の毛をかもじ、腰巻をゆもじと呼ぶのがその一例。同様に、黒い爪楊子も口の中を掃除するもので、ズバリその名称を使うには抵抗があるということで、黒もじになったというのがその論拠である。
クロモジの枝を折ると、快い芳香が周辺に漂う。リナロールやアルコール類を主成分とするクロモジ油の匂いで、その精油は高級化粧品や石鹸の香料に使われる。クロモジ油は、樹液の流動が盛んになる早春、若枝を刈り取り、蒸留して抽出する。今では語り草になっているが、大正時代の初期、政府ではクロモジの植林を奨励したことがある。もちろん香料のクロモジ油を採取して地場産業の振興を図るためのもので、静岡県の伊豆地方はその一大生産地として名を馳せたといわれる。
県内の里山地帯には、植林するまでもなく、いたるところに自生する。薪炭生産が盛んだった昭和の中ごろまでは、炭俵の口止めに用いていたのはクロモジやリョウブの小枝。炭焼き小屋の周囲に群生していたものを刈り取って利用したものである。
なお、クロモジの枝を刈り取り、適当な太さに束ね、これを並べて作ったのが「黒もじ垣」。今でも大きな屋敷の和風庭園で見掛けるが、京都銀閣寺のそれはよく知られる。

クロモジ(Lindera umbellate)は、北海道渡島半島以南の山地に分布するクスノキ科の落葉低木。わが国では、黒文字と書くが、漢名は鉤樟。安永年間に来日した植物学者ツンベルグは、この樹で爪楊子を作ると紹介したことから欧米では、spice bushと呼ぶ。
枝は黄緑色で例外なく木肌に黒い文字模様を描く。葉は、互生につくが、多くは枝先に集まり、対生するように見える。葉身は、倒卵状楕円形で先はとがり、裏面は白色を帯びる。早春、開葉と同時に、冬芽に腋生する1~2個の花芽から、約10個の黄緑色の花を散形状に付ける。雌雄別株で、雌花、雄花とも花弁は6個、雌花はやや小さい。雌株の子房は秋に球型となり、黒熟する。
県内の多雪地帯には、変種のオオバクロモジ(var membranacea)が多く分布するが、沿岸部には基本種のクロモジも自生する。両者の相違点は、葉身が大きいか小さいだけで、その中間型もあって識別は困難な場合が多い。

クロモジの名が文献に初めて現れるのは、江戸時代に編纂された倭訓栞(わくんのしおり)。この書のクロモジの条を要約すると、「樹色黒く、実も黒し、よってこの名がある。延喜式の卯杖(うづえ)(呪具)に使われた黒木であろう」とある。しかし、この説明の前半の文章はともかくとして、後半の記述は誤謬であろうとする説が多い。古代、宮中などで使われた卯杖は椿や梅の材で、クロモジを用いたとする記録は全く存在しない。また、万葉集に黒木を詠む歌が2首収まるが、これらは、「皮付きの丸太」のことで、低木のクロモジは、この黒木に該当しない。
このように、古典とクロモジの関係は極めて薄弱で、これが文学に取り上げられるのは近代に入ってからのこと。
作者は、前にもこのシリーズに登場したことのある備前・足守藩藩主の末裔で、大正時代に活躍した白樺派の歌人。春の日暮れ時、クロモジの半透明な黄色の花に降りそそぐ柔らかな雨をとらえた、いかにも写実的で優雅な歌といえよう。
俳句では「くろもじ」、「黒文字の花」が春の季語。これも短歌と同様、明治期以降の作しか見当たらない。
クロモジの花の咲き方は、散形花序といって、多数の花が一本の軸から側生する集合体となる。これらの句は、その状態と球、壺、かんざしと表現している。
※地衣類:菌類と藻類が共生する下等植物。ブナの樹幹や墓石の面などに生えるのをよく見かける。