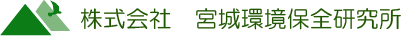暦では立夏(5月5日)から立秋(8月7日)の前日までを夏と定め、俳句もこれに従う。だが、5月はまだ春の気配が残り、夏と呼ぶには少し早い気もする。
今回、季節の花として取り上げたフジの季題は春。ところが東日本では、立夏をかなり過ぎてから咲くので、この季題には違和感がある。全国的にみても「春夏をぶらぶらまたぐ藤の花」の句が正しいようで、平安時代の千載和歌集にも「いづかたににほひますらむふじの花春と夏とのきしべをへだてて」と歌われている。
町内の古刹寿徳寺の南側に位置する千田邸の庭にあるフジは、「子平町のフジ」の名で知られ、仙台市の保存樹林に指定されている。文禄2年(1593年)、藩祖政宗公が朝鮮から持ち帰ったものを千田家が拝領したと伝えられ、300㎡ほどの藤棚に枝を一面に広げている。開花期は5月下旬、1mを超す花房が無数に垂下し、その紫紺の織りなす光景はまさに豪華絢爛。この時期になると所有者は、庭内に自由に立ち入って観賞できる旨の表札を掲げ、来訪者の目を楽しませている。
このほかにも県内には、村田町白鳥神社境内の「奥州の蛇藤」、川崎町支倉の民家が所有する「滝前不動のフジ」などの古木があり、有名である。
フジ(Wisteria floribanda)は、北海道を除く日本全土に分布するマメ科のつる性落葉藤本。山地の林縁部や植林地などで他の樹木に巻きついて生育し、時には地面を這う。花が上品で美しく、昔から庭園木にもされてきた。つるは必ず右巻き(上から見て時計まわり)、太いものは直径20cmを超すものもある。葉は互生につき、小葉が11~19枚の奇数羽状複葉で長さ20~30cm、秋に黄葉する。
花期は前述のように初夏。葉腋から長さ30~100cmの総状花序を垂下する。花は蝶形、通常は紫色であるが、希に白色。花序の基部から下部に向かって咲いていく。豆果の莢はビロード状で、木質化して硬く、初冬、ねじれるように割れて内部の種子をはじき出す。
同属のヤマフジ(W.brachybotrys)は、西日本にだけ分布し、茎は左巻き、花序の長さは10~20cmと短く、花は同時に咲く。
古事記に載る「藤の花衣」の伝説を手始めに、古典にはフジに関する物語や和歌が数多く登場する。なかでも万葉集では人気があり、長歌、短歌をあわせて28首も詠まれている。多くは、フジの満開を歌うもので、それを藤浪と表現しており、ホトトギスと組み合わせた歌も多い。万葉歌の幾つかを紹介する。
太宰府防人司の次官大伴四網の歌。筑紫にもフジの花が揺れる季節になりました。奈良の都をなつかしく思っておられるでしょうね、という意味。時の太宰府長官は大伴旅人である。
自然歌人山部赤人の作。恋しくなったら形見にしてしのぼうと、私の家に植えたフジの花が今、満開であるという意。万葉時代、既にフジが庭に植栽されていたことがわかる。
越中国守大伴家持の歌。ホトトギスが羽を震わせただけでフジの花が散ってしまう。もう盛りは過ぎたらしいというのが大意。この歌は、750年4月9日(新暦5月18日)越中の高岡で作られている。
万葉集を賑わすフジの歌は、平安期に入っても盛んに詠まれているが、古歌はこれくらいにして止め、幕末の歌を一首挙げてみる。
勤皇の志士坂本龍馬の作。つい最近話題になった橋下大阪維新構想の下書きとされる「船中八策」を練っていたときの歌ではないかと思っている。

春と夏をまたいで咲くフジの季題については、既に述べたように、いろいろと物議をかもしてきた。しかし俳句歳時記では伝統的に春の植物として扱っている。元禄期以降、実に多くの句が作られており、そのなかの著名な俳人たちの句を列挙してみる。
これらは江戸期の句である。
1句は「猿蓑」に収まる俳聖芭蕉の元禄元年の作。この句の原案が、「ほととぎす宿かるときの花の色」であることはよく知られている。前書きに「大和行脚のとき」とあり、くたびれはてて宿に着いた夕刻どきの物憂げな気分が十分に伝わってくる。2、3句はともに芭蕉高弟の作。去来の蓑虫は、フジの小枝や葉を丸め、それに糸を吐きつけ巣を作り、その中に住む蛾の幼虫のこと。また許六はフジに関する造詣が深かったようでその著書「百花譜」に「藤は執心ふかき花なり、いかなるうらみか下に持けむ」と記している。
4句は、加賀松任の女流才人千代女の作。春は既に過ぎ去り、夏の気配が漂う時節に咲くフジの花に、お前はほんとうに春の花なのかと問うている句である。
これらは近代の著名な俳人の句である。
1句の山藤は、通常の山地に生えるフジのことで、その長い花穂を揺らす微風を詠んだもので、関西地方に多い花穂の短いヤマフジのことではない。2句は、まさに「子平町のフジ」を髣髴させるものがあり、藤棚の奥の院で藤娘の舞姿が連想される。3句の空谷は、ひと気のない谷間のことで、この断崖渓谷を覆うフジの花盛りを俯瞰した様子。
4句目は1句の作者蛇笏の4男の作。3人の兄の相次ぐ死によって父のあとを次ぐことになり、昭和俳壇の重鎮として活躍した。