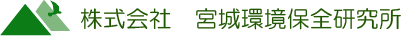拾遺和歌集巻一の春に載る素性(そせい)法師の歌。「あら玉」は掘り出したままのまだ磨かれない玉のことで、新年にかかる枕詞として使われていた。歌意は新しい年がまためぐってきた。次に待たれるのは鶯の声ということ。当時、新年を迎えるということは春を迎えることと同じであった。だが、旧暦の元日は寒さが最も厳しい時期であり、本当の春の到来は鶯の初音を聴いてからであるといっているのである。
閑話休題、わが国の豊かな自然は、定期的に巡ってくる四季の移り変わりによって保たれている。その四季のそれぞれの名称に木扁を添えると実在する樹木の名前になる。椿と榎は簡単に読めるが、楸と柊は難解である。楸はキササゲと読み、ノウゼンカズラ科の落葉高木で秋にはササゲに似た実を結ぶ。そして柊は今月号の季題に取り上げたヒイラギである。
ヒイラギの語源は「疼(ひひら)ぐ」からきており、葉にある刺に触るとヒリヒリ痛むからといわれる。この語源を根拠にヒイラギではなくヒヒラギと発音するのが正しいとする説もある。
ヒイラギの名が初めて文献に現れるのは古事記の景行天皇の条。倭建命(やまとたけるのみこと)に東征を命じた景行帝は、その門出にあたり「比比羅木之八尋矛」を賜ったとある。つまりヒイラギで作った八尋の長さの槍を与えたということである。その後、奈良時代に編集された続日本紀※にも大宝2年正月に、造宮職が八尋の比比良木の庭木を文武天皇に献上したことが記述されている。
余談になるが、この二つの文献でヒイラギの長さがともに八尋(ひろ)というのが注目される。尋とは昔の単位で、大人が両手を左右に広げた長さでほぼ5尺とされている。これを基準として八尋を現在の長さに換算すると12mを超すものになる。このような大木のヒイラギは滅多に存在しないので、ここで言われる八尋とは、とてつもなく大きいという代名詞として使われたものと考えている。
光沢のある常緑の葉に、鋭い刺を持つヒイラギは、昔から魔除けの呪力があると信じられていた。このため大晦日の晩には邪鬼を追い払う目的で民家の戸口にヒイラギの枝を挿す習慣が行われていた。紀貫之の土佐日記にも注連縄にヒイラギの枝を挟み、正月を祝う様子が述べられている。
ところが江戸時代に入ると、この行事は節分の鬼やらいの儀式に引き継がれることになる。立春の前日、ヒイラギの小枝を門口に挿し、更に豆も撒いて鬼を追い出すようになったのである。
ヒイラギは関東以西の照葉樹林内に自生するモクセイ科の常緑小高木。古来、縁起木として東北地方でも民家の門口、参道の入り口などに植栽され、泥棒除けに生垣にも利用されてきた。
樹高は通常7~8m以下。ただし、肥大成長は旺盛で、胸高径60cmの老木もたまに見掛ける。材質は極めて重硬、乾比重は0.95程度を示し、将棋の駒、算盤の玉、櫛などに利用する。葉は対生につき、葉身は長さ3~5cmの楕円形、著しく異なる二つの葉型となり、老木では全円、若木のものは縁に2~5対の大きな歯牙ができる。
雌雄別株で、11~12月に花冠が4裂する芳香のある白色の小花を葉腋に束生する。雌株のものは翌年7月、長さ1.5cmほどの楕円状で紫黒色の果実に成熟し、野鳥の好物となる。
ヒイラギの存在は、古くから古事記などで知られてはいたものの、この木に関わる和歌は全く見出すことはできない。200種近い植物が収められている万葉集にも、ヒイラギにまつわる歌は皆無である。ヒイラギが詩歌として登場するのは江戸時代に入ってからで、節分の行事に関する句が多い。
この時期の季語は「柊さす」である。初句の浜びさし(浜庇)は浜辺の漁夫の家の軒のこと。同じ蕪村の句に<秋風や干魚かけたる浜ひさし>がある。2句目の一茶の赤いわしは、節分の日に、ヒイラギとともに鬼の嫌いな赤いわし(腐れた鰯)も門口に挿していたことに因む句である。
「柊の花」は開花期である初冬の季語。
同じ仲間のキンモクセイの花の香りは強烈でけばけばしい。その点、ヒイラギの匂いには奥ゆかしい芳香が感じられる。
光沢のある濃緑色の葉の間からのぞく清楚な白い花の群れは、まさに初冬を代表する花にふさわしい。そしてそれが音もなくこぼれ落ちる花にも詩的な味わいがある。

※続日本紀(しょくにほんぎ):日本書紀のあとを受け継ぎ奈良朝時代の政治社会経済情勢を編年体で記録した歴史書。