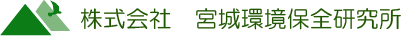11月に入っても、まだ十分に秋の気配が残り、過ごし易い日が続いている。そんなある日、近くにある国見峠の道ばたで、赤く熟したガマズミの実を啄ばむジョウビタキの姿が見られた。
遠い昔を思い起こし、その場で綴った駄作である。私が小学校に通っていたのは、昭和10年代の後半、つまり、太平洋戦争の真っ只中のこと。今とは違って塾などあるはずはなく、学校からの宿題もほとんどなかった時代である。当然ながら下校後の山学校は日課になっていて、気の合った者同志で色んな場所に出かけていった。とりわけ、晴天の日が続く晩秋の山学校は楽しく、かなり奥地の山林まで足を延ばし、クリを拾い、アケビやサルナシをもぎ取り、ガマズミやナツハゼの実をしゃぶるなどして、夢中になって過ごしたものである。しかし、つるべ落としのこの時期は、日の暮れるのが滅法早く、あわてて家路につくのは毎度のことで、時には、山の中にランドセルを忘れてきた苦い思い出もある。
「そぞのみ」は、本県で使われているガマズミの方言で、「よっずみ」と呼ぶ地方もある。里山地帯の至るところに生えている潅木で、紅葉も美しい。初夏に赤い実を枝一杯につけ、はじめは酸っぱいが、徐々に甘みを増していく。山林内での、賦存量はかなり多く、しかも手の届く高さで採取できるので、農村部の子供たちにとっては人気のある野生の食品である。
ガマズミの実は、霜の降る頃になると一段と旨味を増し、シジュウカラやヒヨドリなどの野鳥も群れをなして集まってくる。

ガマズミは、北海道渡島半島以南の日本各地に分布するスイカズラ科の落葉低木。里山の雑木林やアカマツ林など、明るい林床を好み、特に林縁部や林道の沿線に多く見られる。背丈はせいぜい3m以下で、幹は直立し、樹皮は黒褐色、上部で枝を四方に広げ、若い枝は淡褐色で星状毛を密生する。葉は対生につき、葉身は広卵形であるが、さまざまな形態のものもある。葉脈に沿って溝を深く刻み、縁に不揃いの鋸歯がある。
花期は初夏、一対の葉のつく短い枝の先に集散花序をつくり、白色で微香のある小さな花を密生する。「がまずみの花」は初夏の季語で次の句がある。
この花が秋になると長径6mmほどの楕円状の核果となり、赤く色づく。幼年時代は、野生の自然食品として大分お世話になったが、今ではこれを焼酎に漬け果実酒として親しんでいる。
ガマズミの語源に関し、色々な説はあるが、「かま染め」の転訛とする説が有力である。昔は、ガマズミの実の鮮やかな赤紅色を白い布の摺り染めに用いていたからである。カキツバタの名が、紫色の花を白い衣に摺りつけたことから「書き付け花」に転じたことに相通じるというわけである。
万葉集の巻7に作者不詳の次の歌が収められている。
題は比喩歌となっており、真鳥は鷲のことで、卯名手神社は奈良県橿原市(かしはらし)に実在する。万葉集にも詳しい牧野富太郎博士は、この歌の下の句を、白い衣に赤い摺り染めをして着せたい娘が欲しいという恋歌であるとし、この神社の森に生えている「菅の根」は「すがのみ」が正しく、これは、ガマズミのことであると力説しておられる。
平安時代の初期に出たわが国最古の※本草書「本草和名」に莢?(キョウメイ)という名の植物が収録されている。ところがこの植物に和名が記されていないので、その正体については長い間不明のままとなっていた。この植物の素性が明らかになるのは、19世紀に入ってからである。小野蘭山らが著した「本草綱目啓蒙」に、(莢?、ガマズミ、ズミ、山野ニ多シ。小木ニシテ高サ丈許ニ過ギズ・・・・)とあり、これによって莢?がガマズミのことであると判明したのである。
このような事情もあって、俳句で「がまずみの実」が秋の季語に定着するのは明治に入ってからである。
森林調査を終えたあと、甘酸っぱいガマズミの実を噛みしめながら林道を歩いた晩秋の夕暮れが思い出される。
ガマズミの実の傍らにぶら下がる蓑虫も秋の季語である。かつて俳句の先生から、同じ句に季語を二度使ってはいけないと教わったものだが、そんなものには無頓着の句。作者は東京深川生まれで「万蕾」などの句集を主宰された昭和俳壇の第一人者である。
※本草書:薬物として扱う植物、動物、鉱物についての学問書