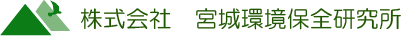11月23日の勤労感謝の日は、戦前も新嘗祭という祝日になっていて、神様に新米を供えてお祝いをしたものである。戦後、名前は変わったものの、勤労を尊び、収穫を喜び合うという同じ趣旨で引き続き祝日に定められている。
仙台市周辺では、この祝日を凡その目安として、晩秋から初冬へと移り変わる。北西の季節風が強まり、冷たい時雨も降り、郊外の里山は枯れ色を増して冬らしくなる。
だが、このままの状態で厳しい冬に直行するわけではない。
この間に何回かは風もなく、穏やかに凪ぐ日もある。これが冬凪、あるいは寒凪といって、初冬の季題になっている。
暖かい日差しを浴び、せわしげにメジロが飛び交う枯れ庭に、ただひとり長い花茎を立てて鮮黄色の花を咲かせているのがツワブキである。
ツワブキは東北地方南部以西の主に沿岸部に自生するキク科の多年草である。耐陰性に優れ、光沢のある常緑の葉と、冬期に咲く数少ない草花として賞用され、古くから庭園、特に坪庭や茶庭に植栽されてきた。
太い根茎から長い柄のある根生葉を数本伸ばし、葉柄の基部には短い鞘が取り巻いている。葉身は、腎円形、長さ10cm、幅30cmぐらいで、フキの葉より厚っぽく、深緑の表面は滑らかでつやがある。ツワブキの名は、艶葉フキの転訛といわれ、漢字ではタク吾(タクゴ、タクは中国語で袋の意がある漢字)と書く。しかし、慣用的には石蕗の字があてられている。
10月下旬頃から30~60cmぐらいの花茎を伸ばし、その上方にキクの花に似た黄色の頭状花を散房状に咲かせる。頭花の縁に一列に並ぶのは雌性の舌状花、その内部を構成する多数の筒状花は両性で、ともに種子ができる。
山陰の小京都津和野の地名はツワブキの野に由来し、もちろん町花にもなっている。
ツワブキに石蕗の字があてられるのは、もともと海岸の岩場や崖地に多く自生するからと考えている。俳句でも「石蕗の花」を冬の季語としているが、この場合、石蕗を「つわ」または「つは」と簡略化して用いるのが一般的である。次の句は、海辺に近い自生地のものを詠んだ句なのであろう。
延宝9年(1681年)、水野元勝によって著された「花壇綱目」にツワブキの名が出ている。このことからしても、江戸時代の初期には既に日本庭園に導入されていたと思われる。次は栽培種をうたったと思われる著名な俳人たちの句である。
続いて近代女流俳壇の大御所的存在の方々の句も紹介してみる。
一句めの「たもとほり」は同じ場所を行ったり来たりすることをいい、二句めの作者は御存知、仙台市で長い間俳句結社「駒草」を主宰されていた方である。
わずかな冬日を集めて、精一杯咲いていたツワブキも、師走に入るころには花期を終え、黒褐色の花茎だけが残る。そんな光景を斎藤茂吉は次のようにうたう。
ツワブキは観賞用だけではなく、食用や薬用としての歴史も古い。早春に摘んだツワブキの若い葉柄を用いて煮物や漬け物などにもするが、これを醤油で佃煮にしたものが正真正銘の伽羅蕗である。
又、前に述べた漢名のタク吾は、ツワブキの葉を揉み、あるいは炙って作った民間薬のことで、腫物、湿疹、切傷の患部に貼ると著効があるといわれる。