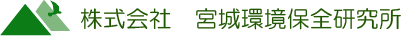雪が消え、真っ先に顔を出すのが蕗の薹。暖かい日差しを浴び、小川の土手や道ばたに群生する光景は、まさに早春の風物詩といえる。
平成14年の歌会始で詠まれた秋篠宮文仁親王の御歌である。
蕗の薹は、食用にされるフキの花序(つぼみ)にあたる部分で、横に這う地下茎から伸びている。長い柄の先に心臓形の葉をつける本体は、花序より少し遅れて芽を出す。
フキ(Petarites japonicus)は、本州、四国、九州の各地に分布するキク科の多年草。湿地を好むが、崩壊地や新しく開けた裸地にもパイオニア種として侵入する。学名(属名)は、ギリシャ語の日除け帽子を意味し、種小名は日本産ということ。通常「蕗」と書くが、これは国字で、わが国で作られた漢字である。
フキの名が始めて文献に現れるのは、平安時代の初期に成立した「本草和名」。この書には、款(かん)冬(とう)=布々(ふふ)木(き)のことと記されており、この「ふふき」が後に短縮されてフキになったと考えられる。
作者は俳諧の祖とされる戦国時代の連歌師。当然、フキの古語がふふきであることを承知の上で、蕗の薹のほろ苦さに天候不順な3月の気候を絡めて面白味のある句にしている。
フキは、雌雄異株である。その花序である蕗の薹は、小さな球型で数枚の鱗片に包まれている。雌株の頭状花は白黄色。小花の縁に多数の雌花が並び、中央に両性花があって種子を結ぶ。
花後は上方に50cm以上も伸び、総状花序に変化し、これが※1薹の字の国訓となる。成熟した種子には冠毛がついて遠くまで飛散する。一方、雄株の頭状花は黄緑色で、不稔性の両性花で構成され、実を結ぶことなく、花後に発達する総状花序も雌株の半分ぐらいの高さである。
北国の蕗の薹は、雪の下で育つので柔らかく、苦味も薄まり季節の食品として人気がある。最も一般的な料理法は、蕗の薹を細かく刻むか摺りつぶして味噌に和え、これに砂糖や味醂を加えて作る。東北地方ではこれをバッケ味噌と呼んでおり、野性味豊かなほろ苦さがあって、酒杯を傾ける肴に適している。なお、蕗の薹の下半分にコロモを付けて揚げるテンプラも人気がある。
蕗の薹は、昔から健康食として利用されていたようで、古い書物には、「蕗の薹、心肺をうるほし、五臓を益し、煩を除き,痰を消し、咳を治す」と結構ずくめのことが書かれている。
東北地方では蕗の薹のことをバッケと称し、かなり知名度の高い方言として使っている。ところが、その語源となると諸説があって、はっきりしていない。地元新聞に連載された「とおほく方言の泉」では、北日本で使われている崖の方言「はっけ」に由来し、これがバッケに変化したものと解説していたが、今一つ説得力に欠け、素直に納得できるものではない。そこでこの際、その語源を探ってみるのも無駄ではなかろうと思い、ネットの書き込みや物知りの知人の意見などを参考に色々検討してみた。その結果、辿り着いたのが、花のようでもあり、つぼみのようでもあるという花序の形態を表す「半開」つまり「はんかい」が、その語源として最も適切であるということに落ち着いたのである。
話は変わるが、八幡2丁目の国道に面して味噌醤油を扱う老舗がある。周辺がすべてRC化された建造物の中、ただ1軒だけ古式蒼然とした瓦葺き2階建ての木造構造物であるため良く目立ち、不謹慎ではあるが地震の都度気にかけていたのである。ところが、今回の3.11大震災に際しても、外見上は無事で、倒壊も免れており、優秀な木造構造物は地震に強いという伝説を如実に証明していたのである。そして、入口の太い柱には、墨痕あざやかに「自家製バッケ味噌発売中」の貼り紙が張られていた。
蕗味噌については既に紹介してあるが、俳句では、蕗の薹、「蕗の花」がともに早春の季語。江戸時代以降、実にたくさんの句が作られている。
初句及び第2句は、江戸期の巨匠の作で、蕗の薹の特殊な形態を詠んでいる。第3句以降は、近世の作で、フキの自生する環境をうたっているが、特に5句目の汀女の作は名句として知られる。汀女の本名は破魔子、1900年熊本市の生まれで高浜虚子に師事し、「ホトトギス」の同人となって女流俳人の育成に努める傍ら、多数の句集や随筆を著した方である。この句は、海岸近くにある線路の土手に芽吹く蕗の薹に※2省線電車や沖合いを通る船舶の汽笛が入り混じって聞こえる夕餉どきの様子を女性特有の柔らかさで詩情豊かにうたっている。
※1:薹(とう):フキやアブラナなどの花をつける茎で、食用になるものをいい、日本独特の意味をあてた国訓である。
※2:省線電車:戦前の鉄道省が運営していた電車で一昔前の国鉄にあたる。