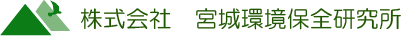10月もおしつまると朝夕の冷え込みが厳しくなり、日中の光も弱まってくる。晩秋といわれるこの時期、近郊の雑木林に足を踏み入れると、薄日の指す林床に赤や紫の実をたわわにつけた潅木が目に止まる。赤色系がガマズミ、紫色系は、ムラサキシキブ。両種とも余程の植物音痴でない限り、その名を知らない人はいない。

ムラサキシキブはクマツヅラ科の落葉低木で背丈は3mぐらい。北海道から沖縄県に至る日本全国の丘陵帯に分布する。小枝は斜上し、葉は対生につく。葉身は長楕円形で、縁に鋸歯があり、両端とも尾状にとがる。花期6~7月、葉柄の付け根に集散する花序を作り、淡紫色の小さな花冠は先端で4裂する。これが秋になると径3mmぐらいの紫色の果実に熟し、小枝に群がってつくさまは極めて美しい。県内では里山の雑木林の中に多く自生しており、これを堀取って庭木として観賞する人も多い。

ムラサキシキブには慣用的に紫式部の字を当てているが、正しい漢名は紫珠である。また学名は、Callicarpa japonicaで、これは「日本産の美しい果実」という意味を持つ。因みに、英語ではJapanese beauty berryといい、これでも華麗な果実に基づく名である。
ムラサキシキブの名前の由来について牧野富太郎博士は、自著の「牧野新日本植物図鑑」で、優美な紫色の果実に平安時代の才媛紫式部の名を借りて命名したものと述べておられる。しかしこれには反論が多く、もともとは江戸時代の末期に、本草学者井岡冽が記述した「大和本草批正」のムラサキシキミを原名としていて、これがのちに優雅な名のムラサキシキブへ転訛したとする説が有力である。
ところでどうゆうわけか、ムラサキシキブに関する記述は、古代の書物に全く出ていない。いろいろな植物を登場させる万葉集や、肝心の紫式部が書いた源氏物語にも、それらしき植物の名は見当たらない。鮮やかな紫の実で人目を引くこの植物は当時の山野にも自生していたはずである。それが古典に出てこないのは不思議なことである。一説によると鎌倉時代、藤原長清によって編纂された「夫(ふ)木集(ぼくしゅう)」という歌集にある、
の「こめごめ」がムラサキシキブの古名であるという人もいるが定かではない。
ムラサキシキブには、ハシノキやハシギの俗名もある。この材は白く強靭で、箸を作るのに適している。山仕事に行き箸を忘れたときは、よくこの木の枝を切って代用にしたものである。また、この材を焼いた木炭は火力が強く、火持ちも良いので鰻の蒲焼には最適といわれる。堅炭で有名な備長炭は、主にウバメガシ(ブナ科)を炭化したものであるが、木炭を記述した古い専門書に「備長は木炭の中の上物なり、紫珠を極上とす」とある。つまりムラサキシキブを焼いた木炭が最上品ということである。しかし、木炭に焼くほど太いムラサキシキブは滅多にあるものではない。
俳句では「紫式部」、や「実むらさき」が秋の季語である。ただしこの季題は最近になって設定されたものらしく、江戸期においても古典と同様、ムラサキシキブを詠じた句は見当たらない。あまりにも華美な紫の色は侘びや寂びを俳句の心とする当時の人たちに敬遠されたのではないかとも思っている。次の句はすべて大正期以降のものである。
ムラサキシキブには果実が白くなる変わり物もあり、これをシロシキブと称し園芸用に植えられる。また、近縁の種として全体的に小振りなものをコムラサキ(これも庭木に賞用される)、葉に毛が密生しビロードの感触のあるものをヤブムラサキといい、ともに宮城県の北部が自生の北限になっている。