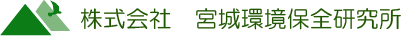旧暦2月の異名はきさらぎ(如月)である。その語源を大槻文彦博士は、きさゆらぎづき(萌揺月)、つまり草木の萌(きざ)し出(い)づる月の転じたものと「大言海」で述べておられる。今年は暖冬の予想を裏切り、厳しい寒さが続いていたが、二十四気の雨水を過ぎるころから気温は上昇し、ようやく春めいてきた。近郊の雑木林には残雪があちこちに見られるものの、木の芽は膨らみ、野鳥の囀りもかまびすしく聞こえるようになった。
江戸時代文政年間の作とされ、北国の里山ではよく見掛ける早春の風景である。
近頃自然志向の高まりから、この寒明けの時期でも、雑木林のなかを歩きながら樹木の冬芽や、雪面に残る小動物の足跡などを観察する勉強会が盛んに行われている。そんな自然観察会に参加したときのことである。散策の途中、案内役の講師から「雑木林で最も早く花を咲かせる植物は?」という質問があった。参加者の多くは、マンサクと答えていたが、なかにはキブシやセリバオウレンと答える少数派もあった。一通り回答が出揃ってから講師の先生は、おもむろに近くの木の枝にぶら下がるねずみの尾のような物体を指差し、「正解は、このハンノキの花です」といって、得意気に花の特徴や形態などを解説するのであった。

ハンノキの花は単性で雄花と雌花は別々につく。雄花穂は、枝先に5cmぐらいの長さで尾状に下垂し、雌花穂は、雄花穂の付け根の近くの葉腋に高さ2cmほどの小さな楕円状になって直立する。両花穂とも小さな花の集合体で、目立つような花弁もなく、よく注意をしないと花とは気がつきにくい。

雌花穂はその後成熟して木質の毬果となる。
ハンノキは、日本全国の山野の湿生地に生えるカバノキ科の落葉高木。根瘤菌を持つので成長は早く、大きくなると直径60cm、樹高20mに達する。鬼首の田代湿原、小野田の田谷地沼、七ヶ宿の玉の木原などには大規模なハンノキ群落が見られ、林床には例外なくミズバショウが群生する。
水田に干拓される前の仙台平野は広大な沼沢地で、ここには一面、ハンノキ群落が分布していた。今でも田園地帯に所在する農家の居久根にハンノキが交じるのはその名残である。少し古い話になるが、コンバインなどの機械化が普及していなかった時代にはハンノキを水田の畦に一列に植栽し、稲架木として利用したものである。
ハンノキは古代から黒褐色系染料の原料として利用されてきた。冬に採取した毬果を釜で煮て、その煎汁で作る茶染めや、毬果を黒焼きにして、その灰で仕上げる黒染めなどの技術は、既に飛鳥時代には確立されていたようである。ちょうどこの時代に編集された万葉集には、ハンノキの染色に関連する歌が14首も詠まれている。その中の一首を紹介してみよう。
い。

住吉の遠里小野の眞榛(まはり)もち摺(す)れる衣(ころも)の盛り過ぎ行く(巻7・1156)
歌中の榛(はり)はハンノキのこと。当時はハリあるいはハリノキと呼ばれており、江戸時代に現在の名に転訛したといわれる。また、初句から二句にかけての固有名詞は、現存する大阪市住吉区の町名で、当時この付近一帯は、ハンノキ林で覆われていた。大意は遠里小野に生えているハンノキで染めた衣の美しい色があせて行ってしまうと嘆いている歌。しかし眞意は、若かったころの美しい容色が、年とともにだんだん色あせて行くと悲しんでいる女性の歌なのである。
俳諧では「榛(はん)の花」が早春の季語。俳句を嗜む人たちは冬木立の枝先に垂れ下がる紐のような物体を、ハンノキの花と心得ているようで、前に紹介した一茶の句以降、たくさんの句が詠まれている。
初句は高浜虚子亡きあとの現代俳壇をリードしてきた巨匠の作、第二句はその子息の句で、父の意志を継ぎ戦後の俳壇で活躍されていたが、惜しくも先年鬼籍に入られた。第三句は、昭和初期の同人誌「ホトトギス」の全盛期を支えた著名な俳人の作で、その作風は客観写生派といわれる。第四句はハンノキの自生する環境がうまく描写されており、この作者には句集「榛の木」もある。第五句は、まさにその通りで、これから農作業は忙しくなる。
ハンノキの材は、強度にバラつきがあって建築材には向いていない。しかし薪炭材としては有用で、特にこの木で焼いた炭は良質な黒色火薬の原料となり、線香花火やデッサンの細字書きなどに用いられる。